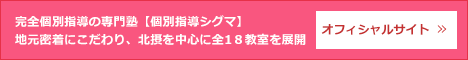9Oct
みなさん、こんにちは。
今回は、リチウムイオンバッテリーの第5回です。
今回の記事は、雑談程度に読んでいただけると嬉しいです。
昨今のリチウムイオンバッテリの利用場面は幅広くなりました。
技術が進歩する中で、既存の技術を用いたバッテリはより安価となり、生産する企業・工場も増えました。
これはリチウムイオンバッテリに限った話ではありませんが、製品の普及が広まり、需要が高まると様々な企業が開発・製作を行います。
一概に質が悪いとは言えませんが、バッテリそのものの質が悪い場合や製品としての安全保護装置に難がある製品もあると思います。
消費者は、それらを判別する知識をつけるか、信頼できるメーカーを頼る術しかありません。
しかしながら、バッテリの製造業者・輸入事業者が信頼できるからといって事故が起こらないわけではありません。
工業製品である上で事故は起こり得るものであり、それらに対する正しい処置を知っておくことが大切です。
異常発熱・発煙・発火に気づいたときには、
①できれば、電源を切る、コードを抜くなどの回路として電気の流れを遮断する
②製品が移動できるような環境であれば、鍋や空き缶などの金属や陶器など耐熱・耐火性の高いものに入れる、
または、金属板の上に置く、周囲にものが無い地面など、延焼可能な環境を遮断する。
もし、水が溜められているバケツなどがあれば、水没させると良いでしょう。
③消火の際にも注意が必要です。急激な燃焼、爆発する危険が伴うため、適切な処理を行えない場合は、周囲への呼び掛けを行うのも手でしょう。
自分自身での対処が可能なレベルの火災であれば、
・化学火災対応の消化器を使用し、消火する。
・大量の水をかけて消火する。
・消火布や砂をかけて、延焼を防止する。
などが対応となるでしょう。
リチウムイオンバッテリは、少量の水をかけると化学反応が進み、より強く燃焼する可能性があります。
水での消火を試みる場合は、必ず水道や屋内消火栓など大量の水が確保でき、水をかけ続けられる状況かを判断しましょう。
また火の手が収まったからとすぐに放水を停止しないように注意しましょう。
リチウムイオンバッテリが十分に冷却されるまで冷却し続ける必要があります。
その時々の環境に応じて対応するとしかお伝えが出来ませんが、周囲の協力を仰ぎ、複数人で対処に当たるようにしましょう。
※消火布と聞くと、私が子供の頃、ポリマー系のリチウムイオンバッテリ(通称:リポバッテリー)を充電する時のために、セーフティバッグをバッテリ・充電器の購入時に一緒に購入したことを思い出します…
話を戻しますが、我々、消費者の製品の扱い方の変化も事故の要因となっている場合もあります。
高価で希少な物であれば、炎天下の車内に置いたままするなどと放置することは控えると思います。
また落下の衝撃によって、内部が破損する場合もあります。
アスファルトやコンクリートなどに落下させた場合はより大きな衝撃が加わります。
より身近に使うようになり、安価な製品が販売され、生活の利便性が向上するとともに、
生活に密着しているからこそ、製品の扱い方もバッテリとしては想定外となっているケースもあるでしょう。
製品の普及に伴い、母数が増えたことで事故が多くなるのも事実です。
2020年から3年間ほどは、国内での製造個数が年間10億個を超えるほど、リチウムイオン電池は製造されています。
ここ1,2年の国内製造個数は減少傾向ではありますが、海外製造や需要は高まり続けています。
今後の動向として、全固体型のリチウムイオン電池の実用化に向けた開発が進んでいます。
市場へ流通する日も近いことでしょう。
全固体型は、液体系と違い液漏れの心配がなく、形状の自由度も高まるとされています。
発火リスクも液体系に比べて低減し、安全性の向上に寄与するものとなるようです。
全固体型のリチウムイオン電池についてはまた機会を設けて、ブログを書いていきたいと思っています。
それでは、また。