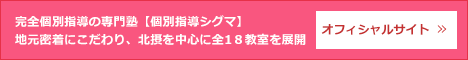7Oct
みなさん、こんにちは。
今回は、リチウムイオンバッテリーの4回目をお届けします。
今日は、リチウムイオンバッテリー自体やリチウムイオンバッテリーを使用した製品に関する処分方法についての記事です。
大きく3つの処分方法があります。
①JBRC 協力店等による回収
②各自治体による回収
③小型家電リユース・リサイクル業者による回収
まずは、
①JBRC会員について見ていきましょう。
一般社団法人JBRCは、小型充電池式電池やそれらを使用する機器のメーカー、輸入事業者を会員として、小型充電池式電池のリサイクル活動を行う団体です。
協力店や協力自治体などから小型充電式電池を回収し、再資源化を推進している団体です。
今回、話題として挙げている、リチウムイオン電池の他に、ニッケル水素電池、ニカド電池を含む計3種類の小型充電式電池を対象に回収を行っています。
しかし、協力店による回収対象は、
・JBRC会員の企業が製造したものであること
・電池種類がニカド電池・ニッケル水素電池・リチウムイオン電池のいずれかであること
・破損、水濡れ、膨張などの異常がある電池、外装のないラミネートタイプの電池ではないこと
となっています。
リチウムイオン電池を含む製品を販売している企業の多くがJBRC会員になっている一方で、
安価な輸入品などのメーカーや輸入事業者は会員に入っていないこともあり、
また長期間使用され、既に電池が膨張している場合は、回収対象外となってしまいます。
回収対象である場合においても、協力店などへの持ち込みが必要であり、少し処分するまでのハードルが高いように感じます。
JBRC会員 企業・回収可能法人名一覧(外部リンク)
協力店・協力自治体検索(外部リンク)
②次に各自治体による回収です。
こちらは各自治体によって回収方法が大きくことなります。
「危険ごみ」や「指定ごみ」、「電池」の回収日に出すことができる自治体もあれば、
市役所や公民館等に設置された「小型家電回収BOX」への廃棄を要する自治体もあります。
ゴミ出しをする際のルールも地域ごとによって大きく異なりますので、ご自身で
「(自治体名) リチウムイオン電池」と調べていただくと処分方法についてのページがヒットするかと思います。
多くの自治体がバッテリの処分の際は、絶縁処理の実施を求めています。
近年のノートPCやスマートフォンは分解しなければ、バッテリを外せないものも多いですが、
2010年代のノートPCや携帯電話では、容易にバッテリを外すことができるものも多くありました。
また電動工具のバッテリなど、バッテリ単体として製品販売をしているものもバッテリ単体で処分することとなります。
構造的にユーザーがバッテリの脱着を想定しているものについては、
バッテリを取り外し、電極(金属が出ている部分)にビニールテープなどを貼り、絶縁を行いましょう。
分解が困難なものや、バッテリの外し方がわからないという方は、
各自治体のホームページを確認し、場合によっては相談の上、現状のままで処分することがオススメです。
現に多くの自治体が、モバイルバッテリーなどは分解せずに排出するよう求めています。
※無理な分解はバッテリの破損・事故につながります。
ただし、その時にも電極部(充電端子)には、ビニールテープなどを貼っておくと良いでしょう。
絶縁用途のテープも市販されており、それを準備することが一番ですが、
家庭で使用される機器のバッテリの多くは36V程度までであり、
スマートフォンなどのUSB機器は5V前後なので、ビニールテープや布ガムテープでも一時的な絶縁処理は可能です。
廃棄する場所が屋外で雨天の場合などは二重三重にしておきましょう。テープの厚みが増すほど絶縁性が上がるのと、水没リスクが低下します。
またすでに破損しているバッテリや膨張している場合には、絶縁処理をした上でお菓子の空き缶などの金属容器にいれることもオススメです。
万が一、発火した際に被害を最小限に抑えられるようにしましょう。
また回収する方が判別しやすいように、内容物を袋などに明記すると良いでしょう。
※もちろん、製品名ではわかりにくいので、「モバイルバッテリ」などの通称や
「リチウムイオン電池 あり」というような感じが良いと思います。
※前述の空き缶など、中身の確認が即時に出来ないものについては、必ず明記するようにしましょう。
③小型家電リユース・リサイクル業者による回収
最後の項目となりますが、こちらも①同様、基本的にはバッテリ自体の損傷がないものが対象です。
一般的にリサイクルショップと呼ばれる店舗で売れるものであれば、売ってしまうのも1つの手でしょう。
ただし、動作不良品や定価が安価なもの、製造元が不明なものについては、買取不可となる場合も多いと思いますし、
それらの品物を処分するためだけに、場合によっては長時間かかる査定を待つことも難しい場合もあります。
家電製品のリサイクルや処分を行っている業者へ聞いてみると、処分してもらえる場合もあります。
リサイクル業者では、個人向けのショップとは異なり、kg単位での取引が多いため、
量が多くなければ買取は難しいですが、無料処分であれば引き受けてもらえるケースもあります。
ただ、こちらは一定程度の知識がある方向けですので、万人にオススメできる方法ではないことも確かです。
大きく3つの方法を説明しましたが、
現実的に多くの方が利用されるのは②かと思います。
①や③は回収場所が限定的である上、処分できるバッテリの状態も限定的です。
そのため、自分自身が住んでいる自治体がどのような回収方法を実施しているかは、きちんと知っておきましょう。
自治体による回収や処分は、回収日が限定的である場合も多いため、回収日までの家庭での保管も必要です。
直射日光が当たる場所や高温となる場所での保管は避け、周囲に燃えやすいものを置かないようにしておきましょう。
上記でも書きましたが、テープで端子部を絶縁処理した上で、お菓子の空き缶や鍋などに入れておくと良いでしょう。
次回、リチウムイオンバッテリ part.5をお楽しみに!